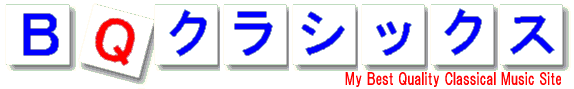
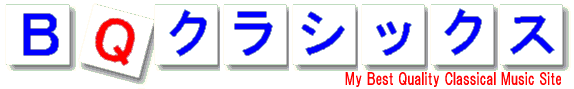 |
|
| TOP|演奏会感想文|廉価LP|コンサートホールLP|廉価CD|資料室|掲示板 |
| ヴァントのバルトークの弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽 |
明晰だが冷たくないバルトーク(戻る)
ギュンター・ヴァントが90才で亡くなった。 ベーム、カラヤン亡き後、 レコード会社の戦略もあって独墺系指揮者の重鎮として、本来地味な指揮者であるヴァントが祭り上げられてしまったように思っていた。 亡くなったことによって、急速に人気がなくなってゆくのではないだろうか、と余計な心配をしている。
このレコードは、ヴァントが30年に渡って関係を持ったケルンのマイナー・オケといってもよいギュルツェニヒ管弦楽団(レコードの表記ではケルン・フィルハーモニー管弦楽団)との録音で、テイチクの1000円盤クラシック・ベスト・コレクション・シリーズにラインナップされたもので、フランスのMUSIDISCからのライセンスとレーベルには書かれている。 なおこのオケとの録音では、この他にも米ノンサッチからベートーヴェンのミサ・ソレムニス(原盤はCulb Francais du Disque,Paris)も持っており、マイナー・レーベルには少なからず録音があるように思う。 追悼盤としてこれらが復活し、ヴァントの音楽が多く残ることを願っている。
さて、このレコードに話を戻す。 ヴァントは後年厳選されたドイツ音楽ばかり振っていたようだが、どれも緻密に構築された音楽であったように思う。 ここで聴くバルトークもそれは全く変わっていないと思う。 非常に明晰な音楽として構築されている。 しかし、バルトークをこのように理路整然と演奏すれば、例えばライナーのように凝縮した冷徹な音楽になりそうなものなのだが、ヴァントにはそれが感じられたない。 かといって暖かい眼差しがあるわけでもなく、荘厳な音楽といえばいいのだろうか。 緻密さと大きさが共存したようなバルトークである。 随所で聴かせるドライヴ感と、それを打ち破るような決然としたティムパニの打音がたまらない魅力になっている第2楽章、ドライブ感にあふれ緊張感と開放感を交互に織りなす第4楽章が実に魅力的。 巨匠になる前の真摯な音楽の奉仕者といったヴァントの演奏である。