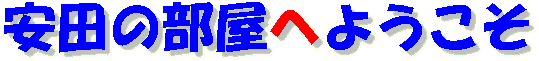
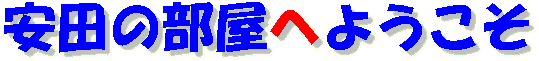 |
|
| TOP|演奏会感想文|廉価LP|コンサートホールLP|廉価CD|資料室|掲示板 |
| POP Music (洋楽編) |
いつもクラシックばかり聴いているわけではありません。
歌謡曲、洋楽なども聴いていますが、中途半端に古くてマイナーなのばかりです。
ここは洋楽を集めました。(笑)
 |
E.C. Was Here (エリック・クラプトン) 1975年 今ではアコースティック・ギターでアンプラグドやってるスローハンドなおじさんと化してしまったエリック・クラプトン30歳のときのライブ・アルバム。 ブルージーで、今聴いても実にカッコ良いアルバムですね。 高校生のときにリリースされたこのアルバム、アルバム・リリース前にFM大阪の「ビート・オン・プラザ」で初めて聴いて打ちのめされました。 その時に録音したカセットを飽きるほど聴きましたね。 素晴らしいギターワーク、バックに「C」や「E」とコードを叫んで合わせながら燃えるさまはまさしく伝説の「ギターの神様」でした。 これこそクラプトン、なんて言ってるのはオールド・ファンゆえでしょうか。 でもカッコ良いんですよね。 A面1曲目「Have You Ever Loved A Woman」冒頭のいきなりのギター、ここから惹き込まれます。 このギター、ジョージ・テリーとのギター・バトルに展開し、実に素晴らしい演奏が続きます。 まさにE.C.ここにありって感じですね。 2曲目「Presence Of The Lord」イヴォンヌ・エリマンとのデュエット。 これでイヴォンヌも気に入って、後日彼女のレコードを買いましたけどね。 今はどうしているのだろう。 それはともかく、途中のクラプトンのギター・プレイ、エキサイティングですねぇ、速くだって弾けるよっていうことね。 3曲目「Drifting Blues」アコースティックに持ち替えて歌うブルース、次第に熱くなってゆきます。 CDではこの続きがあるそうですけど、LPではジョージ・テリーのソロでフェード・アウトです。 B面1曲目「Can't Find My Way Home」ここでもアコースティックで、イヴォンヌとのハーモニーを聴かせてくれます。 オルガンが裏でそっと鳴っているのもいいですね。 2曲目「Rambling On My Mind」このアルバムの頂点はこのブルースでしょうか。 抑え気味の開始から次第に熱くなってゆき、バックに「C」や「E」とコードを叫んで合わせながら燃えてゆくさまはまさしく伝説の「ギターの神様」ですね。 素晴らしいセッションです。 3曲目「Further On Up The Road」軽く流すようなブルースに余裕も感じさせますね。 ヴォーカルも風格あるし、ギターワークもスローハンドっぽいですけど熱いですよ。 最後締めくくるのにふさわしいノリのよい演奏です。 いやぁ〜このクソ熱い夏に、こんな熱い音楽を聴くとかえって気持ちいいですね。 少々若返った気分です。(2005.8.20)
|
||||||||||||||||
 |
キューバン・ムーンライト (スタンリー・ブラックとラテン・アメリカン・リズム) 1960年頃 スタンリー・ブラックの明るく軽やかなラテンのリズムが心地よいアルバムです。 曲の名前と演奏される曲がまったく一致しないほど、収録されている曲については無知なのですけれど、聴いていると、あっどこかで聴いたことがあるかも、なんて懐かしい感じになって最後まで聴いてしまいます。 ラテン・パーカッションをお洒落に取り入れ、リラックスして弾くスタンリー・ブラックのピアノもリリックだけど深みを忘れず、上品な味わいがあってとても素敵です。 ちょっとハイソな大人の趣味が感じられるこんな音楽、大好きです。 御茶ノ水ディスクユニオンのクラシックLPのコーナ、時にムード音楽のレコードも紛れ込んでいるのを発掘するのが楽しみです。 値段の安いものが多いので、たいてい連れて帰ります。 これもその中の1枚です。 ところでスタンリー・ブラック。 1913年6月14日ロンドン生まれ、クラシック・ピアノからスタートしたそうです。 Matthay音楽院を優秀な成績で卒業後、ライト・ミュージックの分野に入ってピアニスト、編曲者として活動、25才の時には南米に渡ってラテン・アメリカ音楽を研究したとのことです。 ちなみに、このスタンリー・ブラックが正統的な指揮者として(というのも変な表現ですが)、グローフェの「グランド・キャニオン」を振ったCDを持っています。 やはりロンドン・レーベルで、(p)1963年、オケはロンドン・フェスティヴァル管弦楽団となっています。 同名の実在するオケが出来る前ではないでしょうか、録音用のオケと思われますが、上品でちょっと華麗な仕上げが感じられる音楽造りが素適な演奏です。 実力者ですね。 さてこのアルバムに話を戻しましょう。 演奏団体名がラテン・アメリカン・リズムとあるように、ラテン・パーカッションを斬新に、といってもとても上品に使っています。 そのリズムに乗せて、スタンリー・ブラックのピアノがリリックで本当に心地よいんです。 声高になることなく、でも安易に流れることもありません。 気付くとリズムがふわっと前面に出てくるような感じ。 その心地よいリズムが気持ちをリラックスさせてくれます。 軽やかでお洒落な音楽、ちょっとハイソな大人の魅力ってこんなのでしょうね。 こんな雰囲気の似合う大人になりたい、そんな憧れもこめて音楽に身を委ねています。(2005.6.20)
|
||||||||||||||||
 |
ヴァンドーム (The Swingle Singers with MJQ) 1966年 先日、新聞にMJQのベーシストだったパーシー・ヒースの訃報が載っていました。 これでMJQの全員が鬼籍に入られたことになります。 ジャズに薀蓄をたれるほど知識はありませんが、1974年のMJQのラスト・コンサート。 スマートでクールなのにやけに熱い演奏が今でも心に残っています。 先日捕獲したスィングル・シンガーズとのレコード「PLACE VENDOME/ヴァンドーム」でご冥福をお祈りしたいと思います。 冒頭は、J.ルイス作曲の「サッシャ(リトル・ダビットのフーガ)」。 スキャット・コーラスが先陣きって歌声を重ねるのに続きMJQが順に追いかける展開の面白いフーガ。 中間部のMJQの演奏も熱っぽいですね。 「アリア〜「組曲第3番」より」、お馴染みJ.S.バッハのG線上のアリア。 ヴィブラフォンによる開始がとても印象的です。 J.ルイス作曲のタイトル曲「ヴァンドーム」、パリで有名な広場の名前だそうです。 明るい饗宴といった感じでしょうか。 「リセルカーレ〜「音楽の捧げもの」より」、これもお馴染みJ.S.バッハの曲。 王の主題をピアノ、続いてヴィブラフォン、そしてコーラスなどで6声のリチェルカーレかしら。 ピアノで始まるあたり第1曲目3声かとも思うけれど、とにかく聴き応えのある演奏です。 B面、「ディドのラメント」、ヘンリー・パーセル作曲による歌劇「ディドとエネアス(Dido and Aeneas)」の第3幕フィナーレ、カルタゴの女王ディドが息を引きとるときのアリアが象徴的にソプラノで歌われています。 冒頭のヴィブラフォン、落ち着いたベースによる終結まで深みを感じさせる演奏です。 「アレキサンダーのフーガ」はJ.ルイスが2歳の長男のために作曲したモダン・ジャズ・バレエ組曲「原罪(Original Sin)」に使われた曲だそうで、技巧的で引き締まったモダン・ジャズ。 「三つの窓(Three Windows)」もJ.ルイス作曲による3重フーガ。 おおもとは1957年のフランス映画「大運河」の曲とのこと。 スローなフーガで渾然一体のアンサンブルとなって全篇を締めます。 なんだかウィスキーが飲みたくなってきました。 最後にこのレコード、(p)1974 \1,300、日本フォノグラム発売となっています。 現在CD化されているものとジャケット写真が違うのと、演奏者が「The Swingle Singers perform with The Modern Jazz Quartet」と書かれています(アマゾンの広告では「M.J.Q.with スウィングル・シンガーズ」ですので主人公が入れ替わってますね)。 なお曲順も、2曲目と5曲目が入れ替わっているようです。 どのような事情によりそうなっているか知りません。 Jazz好きの方は歴史家でもいらっしゃる方が多いようなのでので、念のためにここに記しておきます。(2005.5.6)
|
||||||||||||||||
 |
WISH YOU WERE HERE (PINK FLOYD) 1975年 プログレ、懐かしい言葉の響きです。 いつもはクラシック音楽をメインに聴いていますけど、僕と同世代人は、必ずといって良いほどプログレッシブ・ロック(プログレ)を聴いていたものです。 だから今でもこうやって聴いていますけど、ほんとこのクラシック音楽と親和性の高さは何なんでしょうねぇ、のめり込むように聴いてしまいます。 A面第1曲目の「狂ったダイヤモンド(第1部)」とB面最後の「狂ったダイヤモンド(第2部)」はもともと1つの作品だったものが分割されたそうです。 第1部 13:30、第2部 12:27 足して約26分の大曲ですけど、飽きるってことないですよね。 オルガンのようなシンセの音が厳かさも含んだ開始からどんどんと曲想が展開され、楽器や声の響きも調和し錯綜して、まったくもって現代の音楽ですね。 「ようこそマシーンへ」もまたアグレッシヴな曲ですね、シンセの響きが前衛的でもあって好きです。 7:24 とこちらも長尺、たっぷりと楽しめます。 そしてエンディングの不可思議な効果音も魅力的。 そして「葉巻はいかが」でもエンディングで音域の両端をカットしてラジオのような音にするのもまたカッコ良い、そして意味深長(これが重要)。 「あなたがここにいてほしい」の冒頭はそのままの音質で男女の会話、クラシック音楽の音(何の曲かな、聴いたことありそうだけどな)から始まります。 やはりエンディングでは風の効果音のまま「狂ったダイヤモンド(第2部)」へと繋がる。 シド・バレットへのオマージュでしょうか。 とにかくよく出来たアルバムだと思います。(2005.4.3)
|
||||||||||||||||
 |
西部劇・アクション映画テーマ (サウンド・トラックほか)1971年 8月19日の毎日新聞interactiveに作曲家エルマー・バーンスタインさんの訃報が出ていました。 82歳、詳しい死因は書かれていませんが、最近体調を崩していて睡眠中に息を引き取ったそうです。 この訃報、朝日や読売では出ていないようです。 そんなに無名だったとは思えないのですけど、とにかく「荒野の七人」のサウンドトラックの入ったこのレコードで冥福をお祈りたいと思います。 「荒野の七人」、中学2年生だったかしら、記憶が間違っていないと、家族とは別に初めて友達同士で観に行った懐かしい映画です。 もちろんこのレコードが出た頃のリバイバル上映ですよ。 上本町六丁目の映画館で、この近所にはモデルガン屋さんもありました。 友達に連れてってもらったのもこの時だったかな。 当時のモデルガンはまだ銃身に鉛を詰める規制が出る前で、ちょっと改造すると実弾を打てる構造でしたね。 友達が持っているのを貸してらったりしてました。 当時はマカロニウェスタンが盛んで、友達同士でよくガンマンの真似をしていたもんです。 この映画はハリウッド製ですけど、やっぱり誰がブロンソンで、誰がブリンナー、ロバート・ボーン、ジェームス・コバーンと割り当ててましたけど、童顔で一番頭が良く格好イイのがチコ役(ホルスト・ブッフホルツでしたっけ)なのは決まりでしたね。 で、僕は誰だったかしら?? 村人かな(笑) そんなことはともかくこの音楽、雄大でダイナミック。 ジャケット写真を彷彿とさせます。 あとこのレコード、MAX20と称した20曲入り 2,500円のお買得盤(詰込みで音質はイマイチですけど)。 懐かしがっている人もいるのではないでしょうか。 この「西部劇・アクション映画テーマ」では、007シリーズの6曲がいいですね。 特に1曲目「愛はすべてを越えて<女王陛下の007>」のルイ・アームストロングの歌が魅力的で(ジョン・バリー作曲)、「荒野の七人」とともによく聴いています。(2004.8.21)
|
||||||||||||||||
 |
映画「カルメン」 (サウンド・トラック)1983年 家族旅行に行っていたこともありアントニオ・ガデス氏の訃報を知ったのは、亡くなった翌週、朝日新聞の夕刊に掲載された追悼文によってでした。 7月20日、がんのためマドリードで死去。 67歳だったそうです。 遅ればせながら、追悼の意味をこめ、代表作『カルメン』のサウンドトラック盤にて冥福を祈りたいと思います。 この映画、アントニオ・ガデスの踊りの素晴らしさがとても光っています。 現実の舞台と妄想が渾然一体となってしまうストーリー展開、芸術性の高さなど、カルロス・サウラ監督の傑作であると思うのですけれど、ガデス氏のよくしなる身体の線がとても綺麗で格好良いのが印象的な映画です。 同姓ながら惚れ惚れする踊り(フラメンコ)です。 このレコードからは踊りは想像するしかありませんけれど・・・ さて、このレコードに収録されている声、歌、コーラス、オーケストラによる音楽、そして踊りの足音までも、音楽がばんばんと伝わってきます。 もちろんビゼーの原曲を見事に消化しきっています。 いずれのトラックも素晴らしいのですけれど、やはりガデス氏とも親交があったパコ・デ・ルシアのギター・ワークのセンスの良さ、キレの良さには目を見張るものがあります。 ところで原作のオペラは、先日初めて生の舞台に接することができました。 しかしホセというとガデスのイメージが自分の中で出来上がってしまっているようです。 ちょっと舞台はつらいものがありました。 ガデスは格好良すぎですからね、比べられても可哀想なんですけど・・・どうしても拭えない感じでした。 とにかく『血の婚礼』『カルメン』『恋は魔術師』の3部作はすべてスクリーンで観ましたけれど、『カルメン』が一番素晴らしいのではないでしょうか。 家の中のどこかにあるVTRを探し出すまでは、このレコードでありし日のガデス氏を偲ぶとしましょう (2004.7.31)
|
||||||||||||||||
 |
「華氏96度」 (Third WORLD) 1977年 こう暑い日が続くと聴きたくなるアルバムです。 サード・ワールドはレゲエ(当初はレガエとも言われてましたね)が日本に紹介された1977年当時とっても好きなバンドでした。 ボブ・マーリィ&ウェイラーズがレゲエの本家筋で、サード・ワールドは当時から傍系でしたけどね。 シンセサイザーを使ったサウンドが斬新だったからでしょう。 僕はデビューから3枚のアルバムを持っていますけれど、日本では3枚目に発売されたこの「華氏96度」。 実際には先に発売された「エチオピアへの道」(Journey To Addis)より前のアルバムです。 いずれにしても、このあとサード・ワールドはアメリカに渡ってポップス色がより強くなってしまい、僕の興味から外れてしまいました。 しかしデビューから3枚のアルバムは、メッセージ性を含んだ熱い音楽とリラックスした音楽が同居し、今でも大好きなことには違いありません。 さて、このアルバムの原タイトル「96°In The Shade」は、「華氏96度」と省略されています(「木陰で96度」が正しい訳かな)。 しかもアルバムに収録されたこの曲のタイトルは「1865」。 つまりこの歌は、1865年の華氏96度の熱い日、木陰でさえひどく暑い日、イギリス統治下のジャマイカで叛乱軍の指導者ポール・ボーグルが首吊り刑で処せられたことが歌われています。 アカペラ合唱のあと、レゲエのポップなリズムでリズミカルに歌われているのが(変にアジテーション的でないところが)また素晴らしいところでしょう。 淡々と歌っている。 しかもシンセを使ったサウンドが洗練されてますね。 ところでこの「華氏」という言葉。 最近では「華氏911」。 これ以前では「華氏451」(華氏「911」はこのパクリとも言われていますけどね)、ともに反体制的な意味を持つように感じてしまうのは考えすぎでしょうか。 とにかく、このようなメッセージ性の強い歌は、けっしてクーラーの効いた部屋で聴くものではなく、汗をだらだら流しながら聴くものでしょう。 ゴスペル調のA面1曲目「神の栄光」(Jah Glory)や、2曲目の「種族戦争」(Tribal War)もまたしかり。 特にこの「種族戦争」は繰り返し「Never, Never Have No Tribal War」(種族戦争はもうやめよう)と歌われていますね。 1977年の発売されたレコードですが、悲しいかな今でも No War !! と歌っていないといけません。 人間って進歩していないのかな・・・ でも、ちょっとはましになっていると信じたい。 そんなことを想いながら汗をだらだら流してこの夏もまた聴いています (2004.7.11)
|
||||||||||||||||
 |
「男の世界」 (Jerry Wallace) 1970年 これも実家より持ち帰った17cmEP、いわゆるドーナツ盤です。 ちょっと汚いレコードでしかもチャールズ・ブロンソンが写っていないので(これは貴重品?)、友達から貰ったのかな〜 そんな気がしますがよく憶えてません。 で、やっと音楽に話。 この「男の世界」を歌っているジェリー・ウォレスは、ウェストコーストのカントリー・ウェスタン歌手。 カントリー・バラードが得意な歌手だそうです。 だからB面の「彼女(あいつ)の誇り」(Glory Of The Women)というバラード、ちょっと甘い声でなかなかいい感じですよ。 でもメインはなんたってA面のマンダム「男の世界」(MANDOM - Lovers Of The World)です。 中学時代、よく聴きましたねぇ。 で、再聴してみると・・・CMのイメージから男臭い画面を想像し、ブラスが炸裂、シャウトしているような感じに思えてましたけど、軽く歌ってて明るく爽やかなバラードです。 見事に意識がスリ替わっていました。 改めて新鮮な感覚を憶えました。 でも見事にタイムスリップ。アゴに手をあてて「う〜んん、マンダム」、いい追悼になりました。(2004.6.17)
|
||||||||||||||||
 |
「日本のパット・ブーン」PAT BOONE/TOKYO '64 (Pat Boone) 1964?年 これも実家より持ち帰った17cmLPです。 中学生の頃に近所のお兄さん(酒屋の御用聞きのお兄さん…サザエさんの世界ですね)から頂いたレコードです。 タイトルどおり1964年3月22日の日比谷公会堂における公演のライヴ盤。 今聴いてもパット・ブーンの甘い声は魅力的ですね。 豊かで良き(ここを強調)アメリカを彷彿とさせます。 A面の「思い出のセーラー服」(My Queen In Calico)と「ミスター・ムーン」(Mister Moon)は日本語で歌ってます。 前者はマイナー調でちょっとしんどい感じ(売れない歌謡曲みたない)がしますけど、後者は明るく伸びやかで頑張っていると思います。 やはり英語で歌った3曲目「ワンダフル・タイム」(Wonderful Time Up There)、この曲の前にMCが入って、手拍子してね、みたいないことを英語で(当然ですけど)喋ってて未だにうまくヒアリングできないのがちょっと寂しいけれど曲はアップテンポでいい感じ。 どんどんノッてゆくので手拍子が追いつかず小さくなるのもご愛嬌。 B面は「我が心のサンフランシスコ」(I Left My Heart In San Francisco)「栄光への脱出」(The Exodus Song)の2曲。 やはり前者がイイですね。 これは中学生時代にも好きで何度も聴いてました。 僕にとってのサン・フランシスコのイメージはこの歌といっても過言ではないと思います。 軽く歌いながすように始め、サビの部分では余裕の歌っぷりもカッコイイ。 この後に「砂に書いたラヴ・レター」を収録して欲しかったなぁ・・・と今でも思ってます。 (2004.6.12)
|
||||||||||||||||
 |
パーシー・フェイス・グレーテスト・ヒット (Percy Faith) 197?年 実家より持ち帰った17cmLPです。 来日記念盤と書かれていますが、何年(いつ)のレコードかは不明。 お馴染みの「夏の日の恋」(The Theme from "A Summer Place")、「幸せはパリで」(The April Fools)、「魅惑のワルツ」(Fascination)、「ムーランルージュの歌」(The Song from Moulin Rouge) の4曲が収録されていて600円なので1972年より前だと思います。 お小遣いを使って近所のレコード屋さんで買ったものです。 クラシック音楽を聴き始める以前の中学1・2年生の頃でしょう。 おませさん、だったのかもしれませんね。 パーシー・フェイスを久しぶりに聴きましたけど、滑るような弦楽器がほんと綺麗ですねぇ。 それに軟らかいフレンチ・ホルンも。 軽いビート感がとても心地良よくって、風薫るこんな季節にぴったりの音楽と再会できて嬉しくなります。 おまけに「幸せはパリで」はバカラック作品でした。 女性コーラスにも透明感があって、バカラックの演奏よりも洗練された魅力を感じます。 理屈抜き、しっとりとした音楽が素敵です。 (2004.5.23)
|
||||||||||||||||
 |
クール・ストラッティン (Sonny Clark) 1958年 ジャズに薀蓄をたれるほど知識はありませんが、このクール・ストラッティンは素敵なアルバムですね。 CDでは「+2」として「ROYAL FLUSH」「LIVER」の2曲が追加されていますが、僕が持っているのは1978年の国内再発LP。 A面2曲、B面2曲の4曲構成が僕にはちょうどいい感じです。 まず針を降ろすと名曲「COOL STRUTTIN'」、冒頭のブルースが痺れますね。 有名なアルバム・ジャケットみたく、ちょっと気取って歩くような感じ、たいていの人はこのフレーズを耳にすると、あぁあの曲ね、って思うことでしょう。 文句なしの名曲。 2曲目は「BLUE MINOR」、こちらも日本人好みのマイナー調な曲で(なんでも日本人はマイナー調の曲を持ち波乱の人生があると売れるのだそうです・・・後藤雅洋著「ジャズの名演・名盤」講談社現代新書)、イントロのあとのジャッキー・マクリーン(as)のソロの鈍い響きがカッコ良いな。 とたいていはこの2曲で止めてしまうことが多いけど、B面にひっくり返すと「SIPPIN' AT BELLS」がフィリー・ジョー・ジョーンズ(ds)のいきなりのイントロ・ソロで始まったあとスィングしたソニー・クラーク(p)のソロに移って展開、「COOL STRUTTIN'」でもそうなのですがポール・チェンバース(b)が弓で弾くアルコ奏法のソロが面白いな。 ここまでバップでガンガン来たあと最後はお洒落な「DEEP NIGHT」。 落着いたソニー・クラークのピアノ・ソロにはカクテルが似合う感じがするけど、続くアート・ファーマー(tp)の静かに熱いソロ以降はやっぱバーボンがいいかも・・・ とにかく永遠のアルバムですね。 (2003.11.18)
|
||||||||||||||||
小さな恋のメロディ 1971年 この英国映画のことを懐かしく思えるのは、中学生の頃に実際に映画館で観たことのある今やいい年こいたおっさん達でしょう(苦笑)。 多感な時期、それもまだうつろう陽炎のように淡く揺れる想いを持ち合わせていた頃、この映画を観た人にとってはかけがえのない想い出であるのに違いありません。 そして今、まがりなりにも大人としての分別を持ちあわせてしまったおっさんには、この映画はもう観てはいけない映画であるようにも思います。 でも音楽とは本当に不思議なもので、ここに収録されたビージーズやCSN&Yの歌を耳にすると一気にそんな多感だった時代にタイムスリップしてしまいます。 先日中古レコード店でこのレコードを500円で見つけて買って帰ったのですが、ひょっとしたらこの前の持ち主はその禁断の映画を見てしまった人かもしれないかもしれませんね、そんな風に思ってしまいます。 さてこのLPの中ではやはり「メロディ・フェア」素晴らしいですね。 チェロを使ったイントロからぐっと入り込めてしまいます。 トレイシー・ハイドちゃんは本当に可愛かった… 「若葉のころ/First of May」もストリングを基調にした編曲が素適です。 マーク・レスターくんも可愛かった(けど醜男の僕にとっては内心憎らしかったけど)。 タイトルロールの「イン・ザ・モーニング」もビージーズですが、エンドロールでトロッコに乗った二人が去っていくところはクロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングの「ティーチ・ユア・チルドレン」で、綺麗なメロディとハーモニーに包まれています。 この他にもリチャード・ヒューストン・オーケストラによる演奏曲もありますが、オカリナをヒューチャーしたりいずれもアコースティックな演奏で心に沁みます。 あ〜禁断の映画もまた観たくなってきましたが、遠い夏の日の花火として想い出はそっとしまい込んで時々想い返すのがいいのでしょうねぇ。 (2003.9.6)
|
|||||||||||||||||
タルカス (EL&P) 1971年 Emerson, Lake & Palmer が一躍注目されることになったアルバム。 単音しか出ないミニ・ムーグを駆使したキースのキーボード・プレイに痺れたものです。 当時、クラシック音楽ファンでも若い世代は、必ず、といって良いほどこのようなプログレッシブ・ロックを聞いていたものです。 今聴き返しても多少の作品に好き嫌いはありますけれど、よく出来たアルバムだと思います。 A面はタイトルの「タルカス」は組曲形式で「噴火」「ストーンズ・オブ・イヤー」「アイコノクラスト」「ミサ聖夜」「マンティコア」「戦場」「アクアタルカス」の順で構成されています。 タルカスは創造上もので悪の化身のようなもの。 これが生まれて世の中を破壊しつくす。 そこに人間の顔をしたライオンのようなマンティコアと闘いに勝利して海にもどってアクアタルカスになる。 だいたいそんなストーリーですね。 3人のチームワークが良く、ブルージーなベースとちょっと甘いヴォーカルのグレッグ・レイク、的確なドラミングで文字通り縁の下を支えている感じに思えるパーマーもなかなかカッコ良いです。 キースについては語ることはしなくてもいいでしょう。 B面は小品が並んでいて、ここで好き嫌いは出てくるかもしれませんが、1曲目「ジェレミー・ベンダー」は文句なしの名曲でしょう。 本当に良くコレを聴いたものです。 アップテンポなホンキー・トンク調のキーボードはもちろんのこと、要所でポコっと叩くカウ・ベル、後半には手拍子も入り嬉しくなってきますよね。 わずか1分41秒の曲ですけれど。 (2003.8.3)
|
|||||||||||||||||
 |
マイ・フェア・レディ 1964年 ミュージカル映画最高傑作のひとつ「マイ・フェア・レディ」のオリジナル・サウンド・トラック盤を捕獲しました。 A面8曲、B面8曲、いずれも各シーンを彷彿とさせる内容です。 「君住む街で(on the street where you live)」「踊り明かそう(I could have danced all night)」の旋律を使った「序曲」などオペラと同じ手法ですね。 もちろんこれらの原曲もイライザ(オードリ・ヘプバーン)、フレディ(ジェレミー・ブレッド)の声で入っています(*)。 ドゥーリトル(スタンリー・ハロウェイ)の歌う「運がよけりゃ(with a little bit of luck)」や、イライザ、ヒンギス教授(レックス・ハリスン)、ピッカリング大佐(ウィルフレッド・ハイド・ホワイト)による「スペインの雨(the rain in SPAIN)」などお馴染みな曲を聴きながら、レコード解説・対訳(岡俊男さん)を読み、見開きジャケット中央の映画のカットを眺めるのはほんとうに楽しいものですね。 なおこの映画の音楽総監督はアンドレ・プレヴィンときていますから、サウンド・トラック盤とはいえ演奏自体もなかなか洒落たものになっています。 ただちょっと音質がカサつき気味なのはサントラ盤の宿命かもしれませんね(入手したレコードは国内初版ですがマスタ原盤はどうなんだろ?)。
|
||||||||||||||||
ヘンリー8世と6人の妻 (Rick Wakeman) 1973年 リック・ウェイクマン初のソロ・アルバム。 そしてまた彼の最高傑作と言っても良いのではないだろうか。 その題名のとおり、16世紀の初めのイングランド王であったヘンリー8世の6人の妻たちについて、一人1曲を割り当てたアルバムである。 これが出た当時、僕はEL&Pのような派手なパフォーマンスのグループに目がいっていたこともあって、リック・ウェイクマンは(このあとも続いた「地底探検」や「アーサー王と円卓の騎士」もあって)出来合いの音楽(ロックのノリや自由さからちょっと離れた標題音楽)として一段低く考えていたが、今になって聴き返してみるとなんと愚かな考えであったことかと思わざるを得ない。 さてこのアルバム、 Side.A「アラゴンのキャサリン」「クレーヴのアン」「キャサリン・ハワード」、Side.B「ジェーン・シームーア」「アン・ブーリン」「キャサリン・バー」の6曲から成っている。 この中のどの曲をとっても完成度は高いのだが、今回聴き返したなかではSide.Bの冒頭、オルガン・ソロで始まる「ジェーン・シームーア」を一番にしたい。 バロックとロックの融合体というよりもバロックそのものといっても過言ではないほどのクオリティの高さにしびれる。 またこれに続く「アン・ブーリン」では一転してブルージーなジャズ・ピアノを聴かせるあたりも本当に巧いものだ。 「音の魔術師」などと呼ばれたりもしたが、これらを聴くだけでも基本的なキーボードのテクニックはキース・エマーソンの比ではないように思われる。 そして曲へのアプローチも実に巧くて驚くばかり。 納得度の高い演奏がぎゅっと詰っている。 1973年当時、単音しか出せなかった電子オルガンを駆使してのこの完成度の高さに驚くばかりである(逆に制約が多かったことが完成度の高さに結びついているかもしれないけれど)。 (2003.4.30)
|
|||||||||||||||||
ハッピー・セッション (Benny Goodman) 1958年 始めて買ったジャスのアルバム。1973年頃だったろうか、クラシック廉価盤のヒットに気を良くしたのか各社からジャズの廉価盤が出された。
このレコードもそうしたソニーのシリーズの1枚で、ベニー・グッドマン(cl)のアルバムだが、当時すでにロンドン交響楽団の常任指揮者として活躍していたアンドレ・プレヴィン(p)も加わったもの。
プレヴィンの演奏は2曲のみだったけれど、タイトルどおりのゴキゲンなサウンドでした。
以降、再発が多くなって面白くなくなったクラシック廉価盤にかわってジャズのレコードも集めるきっかけになったことも懐かしい。
|
|||||||||||||||||
マントヴァーニ・タンゴ・アルバム 1961年 ディスクユニオンのクラシック中古LPコーナから300円で捕獲したもの。
マントヴァーニ楽団の弦楽器を主体にしたムード音楽が心に沁みます。
|
|||||||||||||||||
グロリアス20 カンツォーネ 196?年 友達の影響から小学校5年生頃からラジオを聞くようになって、テレビから流れる歌謡曲とは違う音楽の世界があるのを知りました。
いわゆる洋楽への目覚めですね。
日本のGSよりもポップスがいい、なんて口走ってラジオのポップス番組をよく聴いていました。
当時は今のようにヒット曲がめまぐるしく変わるのではなく、ヒット曲の生きも長く、今から考えても1965年頃のヒット曲もよくラジオから流れていました。
なかでもどこかに明るさを感じるカンツォーネが好きでした。
今でもあるようですが、当時のサン・レモ音楽祭はとても権威があり、その優勝曲がヒットする図式がありましたね。
ジリオラ・チンクェッティの'64年の「夢見る想い」や'66年の「愛は限りなく」、ボビー・ソロの'65年の「君に涙とほほえみを」などは優勝曲で、。
そして僕がラジオを聴き始めた1969年当時のラジオからも流れていましたし、この年はチンクェッティの「雨」(入賞曲)が大ヒットしていました。
失恋の歌でも、どこかカラっと陽気で明るく、貧しくてもなんとかなるさ、という感じで元気が出てきます。
|
|||||||||||||||||
THE BEST BURT BACHARACH 1971年 ディスクユニオンのクラシック中古LPコーナには時々こんなのも混じっています。 キング・レコードの企画物のバート・バカラックのベスト盤を180円で捕獲しました。 8曲入りで1,000円という定価は当時のクラシック1,000円盤に合わせていたのでしょうか。 とにかく僕がクラシック音楽を聴き始める直前に聴いていた懐かしい曲が彼のオーケストラの演奏で入っています。 懐かしくて涙がちょちょ切れる・・・ とはオーバーですけど、「雨に濡れても」は映画「明日に向って撃て」のテーマでB.J.トーマスの歌でヒットした曲、「恋よ、さようなら」はミュージカル「プロミス・プロミス」の曲ですがディオンヌ・ワーウィックの歌でヒットしましたね。 この2曲は中学生の時にシングル盤で買いました。 かなりのお気に入りです。 この他に「サン・ホセへの道」「愛を求めて」もディオンヌ・ワーウィックの歌、「遥かなる影」はカーペンターズでヒットした曲でしたね。 「恋するメキシカン」「エイプリール・フール」「恋のおもかげ」なども誰かが歌っていたように思いますが(思い出せませんが)どこかで聴いた曲ばかりです。 当時はレイモンド・ルフェーブルやポール・モーリア、パーシー・フェイスなどのオーケストラも活躍していましたが、バート・バカラックのカラっとしたアメリカン・サウンドは垢抜けててとっても魅力的でしたね。 (2002.9.18)
|
|||||||||||||||||
PLAY BACH / Vol.4 フランスのジャック・ルーシェ・トリオによるJ.S.バッハのアルバム。 ディスク・ユニオンの100円コーナに店員が補充したのを間髪を入れずに捕獲した。 噂には聴いていたジャック・ルーシェの PLAY BACH だが、予想を遥かに超えた素晴らしいアルバムだった。 このアルバムでは平均律クラヴィア曲集という格好の素材を使って、巧みにツボを押さえた演奏が心地良い。 「前奏曲第1番」「フーガ第1番」「前奏曲第2番」などでは、ジャック・ルーシェのソロがほぼ原曲のとおり出てくる。 とにかくこれがとてもしっかりした演奏である。 さすがにコンセルヴァトワールでイーヴ・ナットに師事していた実力だろう。 ここにベース、ドラムが最初おつきあい程度に入ってくるが、しだいに3者の演奏によって主題が盛りあがってきたら、一転してアグレッシヴな自由なジャズ演奏をややアグレッシヴに演ったあとすっと原曲にもどって終わるという形式。 心憎いほどのオーソドックスさだが見事な聴かせ上手。 またフーガになると、ドラム(クリスチャン・ギャロ)、ベース(ピエール・ミシュロ)が活躍して音楽の広がりが増すけれど、この二人の出過ぎないスィング感と、きちんと要所を押さえた安心感が素敵である(「フーガ第2番」「前奏曲第5番」「フーガ第5番」)。 そして「トッカータとフーガ ニ短調」では、お馴染みのトッカータの冒頭を実にそれっぽく始めるのが面白い。 どの曲も原曲をとても大切にしているのがよく分かるし、自分達の演奏もきちんとそれにマッチさせて展開している大人の巧さというものを感じる。 そういえば最近、こんな大人向けの音楽をあまり耳にしないように思う。 (2002.7.20)
|
|||||||||||||||||
IN AND OUT OF FOCUS (FOCUS) 1970年 オランダのプログレロック・グループのFOCUSのデビュー盤(これは1973年にSire Recordsから再リリースされたもの)。 タイス・ヴァン・レアーのトリオ(マーティン・ドレスデン:bg、ハンス・クラーヴァー:ds)にイヤン・アッカーマンが加わったのが1969年、いわゆる古いFOCUSのアルバムである。 まだタイス・ヴァン・レアーのライアライア... というファルセットの歌は聴けないが、A面1曲目の「FOCUS」から約10分にも及ぶインスト曲で始まる。 今で言うところのフュージョンのセッションを聞くような先取り感覚が味わえる。 しっとりと時には熱く演奏を展開しているが、どちらかというと音量の大きさで熱さを出している風でもあって発展途上系だろうか。 「WHY DREAM」もオルガンとギターのパートが分かれていてバトルにならないのが後年と違うところか。 「HAPPY NIGHTMARE (MESCALINE)」はジャズ・フレーバーの強い演奏。 B面の「ANONYMOUS」は冒頭とエンディングはどこかバロック調だが、すぐにタイス・ヴァン・レアーのフルートとイアン・アッカーマンのギターのバトルになるフュージョンっぽい味わいがとても強い7分のインスト曲。 途中からピアノ・ソロ、ついでベーソ・ソロへと続きジャムセッションが展開。 実にカッコ良い。 グループとしてとてもよく纏ったところを聴かせてくれる。 「BLACK BEAUTY」は耳当りのよい歌。 ラストは「FOCUS」のヴォーカル入りヴァージョン(2:44)でしっとりと終わる。 タイスとアッカーマンの二人の個性よりもグループとしての音楽に力点が置かれたようなアルバム。 なお国内盤でリリースされたときには「ハウス・オブ・キング」が追加されていたようだ。 (2002.6.16)
|
|||||||||||||||||
ELLA & LOUIS 1956年 リラックスしたい時に聴くアルバムのひとつ。 ルイ・アームストロングとエラ・フィッツジェラルドのVerveレーベルでの共演アルバム。 この1年後には「ポーギーとベス」も残しているが、ここではリラックスし、息のあったボーカル・デュオを存分に聴かせてくれる。 またバックも豪華で、ピアノはオスカー・ピーターソン、ベースはレイ・ブラウン、ドラムにバディ・リッチ、ギターはハーブ・エリスでの1956年、ロス・アンジェルスでの録音である(モノラル録音)。 オスカー・ピーターソンのピアノから軽くフェイクして歌い始める1曲目「Can't We Be Friend」、ルイが大胆なフェイクで引きとり、トラッペット・ソロのあとリラックスしたデュエット。 このあと、曲が「Isn't This A Lovely Day」「Moonlight In Vermont」とかわってもほとんど夢見心地。ガーシュウィンの「They Can't Take That Away From Me」のルイのスキャットを一緒に口ずさみ、心地良いスウィング感がたまらない。「Under A Blanket Of Blue」「Tenderly」でのルイのトランペット・ソロは情感あふれた素晴らしさだが、エラの歌もまた素晴らしく、特にA面ラストでルイの物真似のスキャットも洒落ている。 B面は明るいルイの歌声によるガーシュウィンの「A Foggy Day」で始まり「Stars Fell On Alabama」でのスキャットのデュエット、そしてお馴染みの「Cheek To Cheek」のコミカルなルイとドライブしたエラのデュエットでこのアルバムの最高潮に達した感がある。 「The Nearness Of You」はエラによる甘いラブソング、「April In Paris」もエラのデリケートな唄だが、いずれもルイが優しく唄とトランペットで絡んでこのアルバムを閉じる。 夜に一人で静かに楽しみたいアルバムである。 (2002.1.4)
|
|||||||||||||||||
Tapestry (Carole King) 1971年 歴史的名盤といえるキャロル・キングの「つづれおり」。 中学生の頃、ラジオから流れていた「It's Too Late」が脳裏から離れず、高校生の時にようやく心斎橋ミヤコの店頭セールで見つけて買った直輸入盤。 クラシック以外では初めて買ったPOPSのオリジナル・アルバムである。 これはキャロル・キングのとても私的な内容のアルバムとのことだが、ストレートかつファンキーに歌いあげており、どの曲も実に素晴らしい。 初めて買ったPOPSのオリジナル・アルバムということもあり、何度もジャケットを眺めまわしていたが、しばらくして見開きジャケットの裏の小さな文字が歌詞であること、さらにそれより小さく印刷されているのが演奏メンバーの名前と楽器であることに気付いて驚いた。 今では別に驚くほどのことでもないが、さすが洋楽のアルバムは違うなぁ… と感心したものである。 そしてこれをよく見ると「You've Got A Friend」は弦楽四重奏とアコースティック・ギター、コンガとピアノ。 「It's Too Late」はドラムス、エレキベース、ピアノ、エレクトリック・ピアノ、エレキギター、コンガ、ソプラノサックスのセッション。 また「Home Again」は印刷上2行で歌詞が収められ、ドラム、ストリング・ベース、アコースティック・ギターとピアノ。 そしてタイトル曲の「Tapestry」はキャロル・キングのキーボードの弾き語りである。 最小ともいえる構成で、そしてこんなに存在感のある演奏が繰り広げられているなんて。 実にシンプルでストレート、そしてオーソドックス。 本当に素晴らしいアルバムである。 そしてこのアルバムを締めくくるのは別れた夫であるGerry Goffinとの合作のカバー曲をストリング・ベースとキャロル・キングのピアノで唄った「(You Make Me Feel Like)A Natural Woman」である。 (2001.12.5)
|
|||||||||||||||||
Robin Trower LIVE ! (Roibn Trower) 1976年 イギリスのロック・ギタリスト Robin Trower(グループ名も同じ)の1975年2月3日ストックホルム・コンサート・ホールでの白熱したライブ録音。 ロックも最近ではファッション化が随分と進んで耳障りの良い音楽に成り下がってしまったように思うが、このアルバムにはスピリットと、何より素晴らしいギター・ワークがある。ブルース感覚を充満したまさしくギタリストのアルバムである。 Robin Trower のセカンド・アルバムからフューチャーされたB面1曲目「LEDY LOVE」とB面最後の「LITTLE BIT OF SYMPATHY」の高揚感が素晴らしい。 ライブによるごまかしの効かないトリオ演奏ならではスリリングさもある。 Robin Trower は Jimi Hendorix の影響を指摘されるが、確かによく似たギター・ワークである、B面3曲目「ALETHEA」でのワーワーペダルの使い方や、A面最後の「ROCK ME BABY」でのボーカルのメロディ・ラインとおなじフレーズをなぞるようにギターでも歌うなど Jimi を彷彿とさせるものがある。 しかし単に Jimi のコピーとしてとどまっていない。 同じ語法を用いてはいるが、より完成された Robin Trower というグループでのブルースの世界がある。 それはA面1曲目「TOO ROLLING STONED」からに顕著に現れている。 ブルース感覚あふれたファズ・トーンのリズム・ギター、セクシーなリード・ギターを見事に弾きわけている Robin Trower、ノリの良いヴォーカルと堅実なベースの James Dewar、確実なテクニックでたたみかけるようなドラミングを展開する Bill Lordan 。 もっと知られて良いアルバムだと思う。 (2001.8.26)
|
|||||||||||||||||
HAMBURGER CONCERTO (FOCUS) 1974年 オランダのプログレロック・グループFOCUSのアルバム。 A面1曲目「DELITE MUSICAE(リュートとリコーダの為の小品(音楽の歓び)」から2曲目「HAREM SCAREM」へと続く2曲が最高。 クラシックとロックを融合させた試みはEL&Pの「展覧会の絵」など色々とあったが、完成度という点ではこのアルバムの方が高いと思う。 タイス・ヴァン・レアー(英語読みだとティッジス・ファン・レール)の多彩な才能とヤン・アッカーマンのエモーショナルなギターやリュートのプレイが融合された見事なアルバムである。 「BIRTH」でのフルートやシンセサイザーとギターのインタープレイも聞き応えがある。 このアルバムでは前作までの単調なピエール・リンデンに代わってコリン・アレンが巧いドラミングを聴かせているのが幸いしている。 ベルト・ルイターは変わらず勘所を掴んだ的確なベースである。 B面は20分に及ぶタイトルロール「HAMBURGER CONCERTO」1曲のみ。 コンチェルトというよりも管弦楽組曲という感じだが、お馴染みのタイス・ヴァン・レアーのライアライア... というファルセットの声も入って全く飽きさせることのないプレイが展開されている。 この当時のロックの完成度の高さをまざまざと聴かせるアルバムである。 (2001.5.2) |